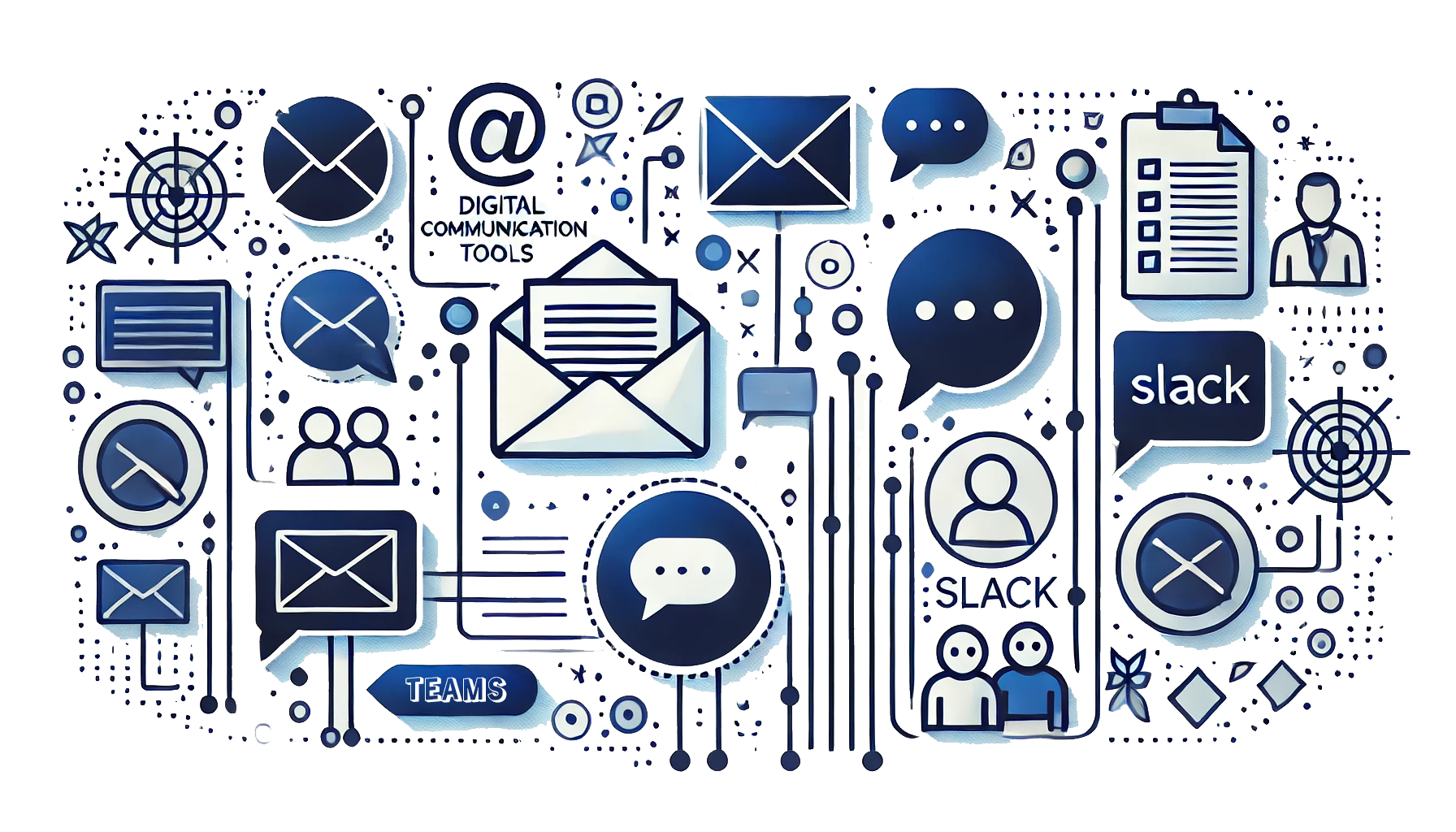本記事では、テキストコミュニケーションにおける基礎スキルや対応の工夫について考えます。
1. はじめに:テキストコミュニケーションの重要性と背景
テキストツールが求められる理由
現代の大学環境では、デジタルツールを活用したコミュニケーションが必須となっています。特に、メールやチャットツールは、学生と教職員が場所を問わずスムーズに情報を共有し、支援を行うための手段として広く利用されています。一方で、学生は、デジタル環境で成長していますが、必ずしも全員が適切なコミュニケーションスキルを備えているわけではありません。文部科学省(2021)の調査によると、デジタルコミュニケーションの利便性は高まっている一方で、適切な使い方やコミュニケーションスキルの不足が問題となることも指摘されています(引用:新型コロナウイルス感染症の影響による学生等の学生生活に関する調査(結果))
テキストコミュニケーションのメリット・デメリット
まずメールとチャットツールそれぞれの特徴を整理し、どのような場面で有効か、また注意すべき点を解説します。
(メールの特徴)
- フォーマルである
正式な要件や依頼を送る際、メールは相手に誠実で礼儀正しい印象を与えます。 - 履歴の保存が容易
メールは時系列で管理されやすく、過去のやり取りを確認するのに便利です。 - 詳細な内容の伝達
長文で要点をまとめて伝えることができ、説明が必要な要件に適しています。
- 即時性が低い
返信に時間がかかる場合があり、緊急のやり取りには不向きです。 - 誤解を生む可能性
文面のみでのコミュニケーションは、トーンやニュアンスが伝わりにくいため、受け手が誤解することもあります。
(チャットツールの特徴)
- リアルタイム性
即時にメッセージをやり取りできるため、緊急時や短い確認に便利です。 - 気軽なやり取り
スタンプや絵文字なども使いやすく、リラックスした雰囲気でコミュニケーションが行えます。 - チームでの情報共有が容易
複数人のグループチャットで、情報を一度に共有しやすい点が魅力です。
- カジュアルすぎる場合がある
特に公式な内容や重要な要件には、チャットツールでは軽率な印象を与えることもあります。 - 集中力の妨げ
即時性が高いため、頻繁な通知が集中を妨げる可能性があります。
メールやチャットツールを使ったテキストコミュニケーションは、学生とのやり取りにおいて時間や場所の制約を超える重要なツールです。しかし、一般にテキストを用いたコミュニケーションでは、口調や表情が伝わりにくく、意図が誤解されるリスクも伴います。テキストメッセージのやり取りではメッセージ内容の30%ほどが誤解されるとする研究もあります。
特に、デジタルネイティブ世代の学生は、短いメッセージやスタンプ、絵文字などに慣れているため、長文のメールや丁寧な文章構成が読みづらく感じることが少なくありません。
2. 教職員が学生に伝えたいデジタルコミュニケーションの作法
テキストを用いたコミュニケーションでは、対面での会話よりも慎重な配慮が求められます。ここでは、大学教職員が学生に指導すべき基本的なポイントを示します。

敬語と適切な言葉遣い
メールやチャットでのやり取りにおいては、敬語の使用や適切な表現が重要です。特に初対面の教職員に対して、友人と同じような略語やスタンプを多用するのは避けるべきです。
教職員は、メールのフォーマットや一般的な挨拶の例を学生に教えると良いでしょう。また、身近な先輩等に一度チャックしてもらうよう学生に提案するのも良い方法だと思います。
明確な要件と簡潔な表現
学生がメールを送ることに手間取っているようでしたら、「用件を端的に」「無駄なく簡潔に」伝えることを推奨します。件名を使い、本文で用件を簡潔に述べることで、受け手にとって分かりやすいメッセージとなります。例えば、「◯◯の件で相談したいのですが、◯日◯時に空いていますか?」など、具体的に相手のアクションがわかるような表現が適切です。
返答への感謝と締めくくり
メッセージの最後に、「お忙しいところ、ご確認いただきありがとうございます」、「どうぞよろしくお願いいたします」などの言葉を加えることで、礼儀正しい印象を与えると伝えます。特にメールでのやり取りが苦手な学生にとっては、こうしたフレーズを習慣にすることが重要です。
3.テキストコミュニケーションが特に苦手な学生への対応
一部の学生は、メールやチャットの形式的なやり取りに極端な苦手意識を持っています。彼らに対して教職員ができるサポートをいくつか紹介します。
- テンプレートを活用させる
-
初めて送る内容のメールを送る際、文例があると非常に助けになります。
- 「初めての問い合わせ」、等のテンプレートを配布する
- Web上で必要なテンプレートを検索させる
- ChatGPT等の生成AIを使って文面の雛形を作るようアドバイスする
- チャットツールの活用
-
デジタルコミュニケーションが苦手な学生に対しては、定期的にメールの内容ややり取りについてフィードバックを行う場を設けることも効果的です。例えば、月に一度、学内のラウンジなどで「コミュニケーション相談会」を実施し、学生が実際に送ったメールについて振り返る機会を作ることで、実践的にスキルを磨くことができます。
- 研究室の「日報」などは、Slackなどのチャットツールの方がメールよりも取り組みやすいと感じる学生が多いようです
- 休学明けなど、継続的な登校ができているか心配な学生の状況を確認するツールとしても優れています(本人からの“今日も来ています”などの短いメッセージで確認)
- 定期的なフィードバックの場を設ける
-
デジタルコミュニケーションが苦手な学生に対しては、必要に応じて対面でのフォローを行います。
たとえば、定期的に個別の相談時間を設けて、メールの内容や返答の仕方について指導することで、学生の不安を和らげることができます。
- 忙しい教職員の時間を取ることを気にする学生は多く、定期的な相談のメリットはその障壁を和らげることです
- 定期開催の頻度は、目的や双方の負担感に照らして決めると良いと思います
4. まとめ:
(1)デジタルコミュニケーションスキルの学びは、将来の社会生活や職場でのスムーズなやり取りにも大いに役立ちます。
(2)教職員の皆さんは、学生にテンプレートやメール構成の具体例を示し、実践に基づいたフィードバックを行うことで、彼らが自信を持ってコミュニケーションを取れるようサポートできます。学生にとっても、これらのスキルは自己表現や信頼関係の構築に貢献します。