1.はじめに:言葉にならない“メッセージ”に目を向ける
学生とのやりとりの中で、「何を言うか」以上に、「どう言うか」が大切になる場面は少なくありません。
特に、学生が不安や緊張を抱えている状況では、教職員の身振りや表情が、学生に大きな安心感や、逆に不安を与えることがあります。
心理学の研究によれば、人が受け取るメッセージの多くは言葉そのものではなく、口調や態度、視線や身振りなどの非言語的要素に影響されることが分かっています。これは「メラビアンの法則」としても知られています。
今回はその中でも「ジェスチャー(身振り手振り)」に焦点をあて、学生との信頼関係構築に役立つ活用法を紹介します。我々カウンセラーも、カウンセリングを行なっている自分の身体や体の動きに、少し引いた視点から客観視するようにと訓練されており、この記事では、そうした視点を踏まえて、大学教職員の皆さまにもすぐに実践できるポイントをお伝えしていきます。
2. 非言語コミュニケーションとしてのジェスチャー
ジェスチャーは、私たちが言葉をより明確に伝えたり、感情や意図を補足・強調するために自然と用いている身体の動きです。例えば、何かの大きさを手で示したり、うなずきとともに「なるほど」と伝えたりするのも、立派な非言語コミュニケーションです。
心理学では、ジェスチャーは以下のような機能をもつとされています(Kendon, 2004)。
- 象徴的機能:ジェスチャーが持つ特定の意味を表現する *文化の差異に注意
-
例:OKサイン👍、手を振る👋
- 補足機能:言葉のリズムや強調したいことを手の動きや体の動きで支える
-
例:ここまでやってみよう(手で区切りを表現)
たとえば、話の節目に手で空間を区切る動きは、説明の構造を視覚的に示す効果があります。
- 感情表出機能:こちらの気持ちを体で表現する
-
例:手を開いてオープンさを表現、腕を組んで固辞や威嚇を表現
これらの動きは必ずしも意識的に行っているとは限らず、話し手の心理状態が無意識に表れることもあります。
カウンセラーである我々もそうですが、教職員としては、無意識の動作が学生にどのような印象を与えるかを、時に振り返ってみることも大切だと思います。
Kendon, A. (2004). Gesture: Visible Action as Utterance. Cambridge University Press.
3. 実践例:学生との関わりにおける活用
事例1:緊張して話す学生への対応
ある学生が就職活動の面接練習で極度に緊張し、視線も定まらず言葉に詰まっていました。
指導教員が、うなずきながら手を前に開いて「大丈夫、続けて」と静かに促すと、学生は少しずつ落ち着きを取り戻し、最後まで話し切ることができました。
ここでの「手を広げるジェスチャー」は、受容と安心を示す非言語的サインとして機能しました。

事例2:説明の明確化
修学相談で、ある学生に複雑な履修ルールを説明する際、教職員は、ホワイトボードを使いながら、手で関係性を示しつつ話を進めました。学生は「やっと分かった気がします」と反応しました。
ジェスチャーが視覚的な補助となり、認知負荷を下げる効果があったと考えられます。
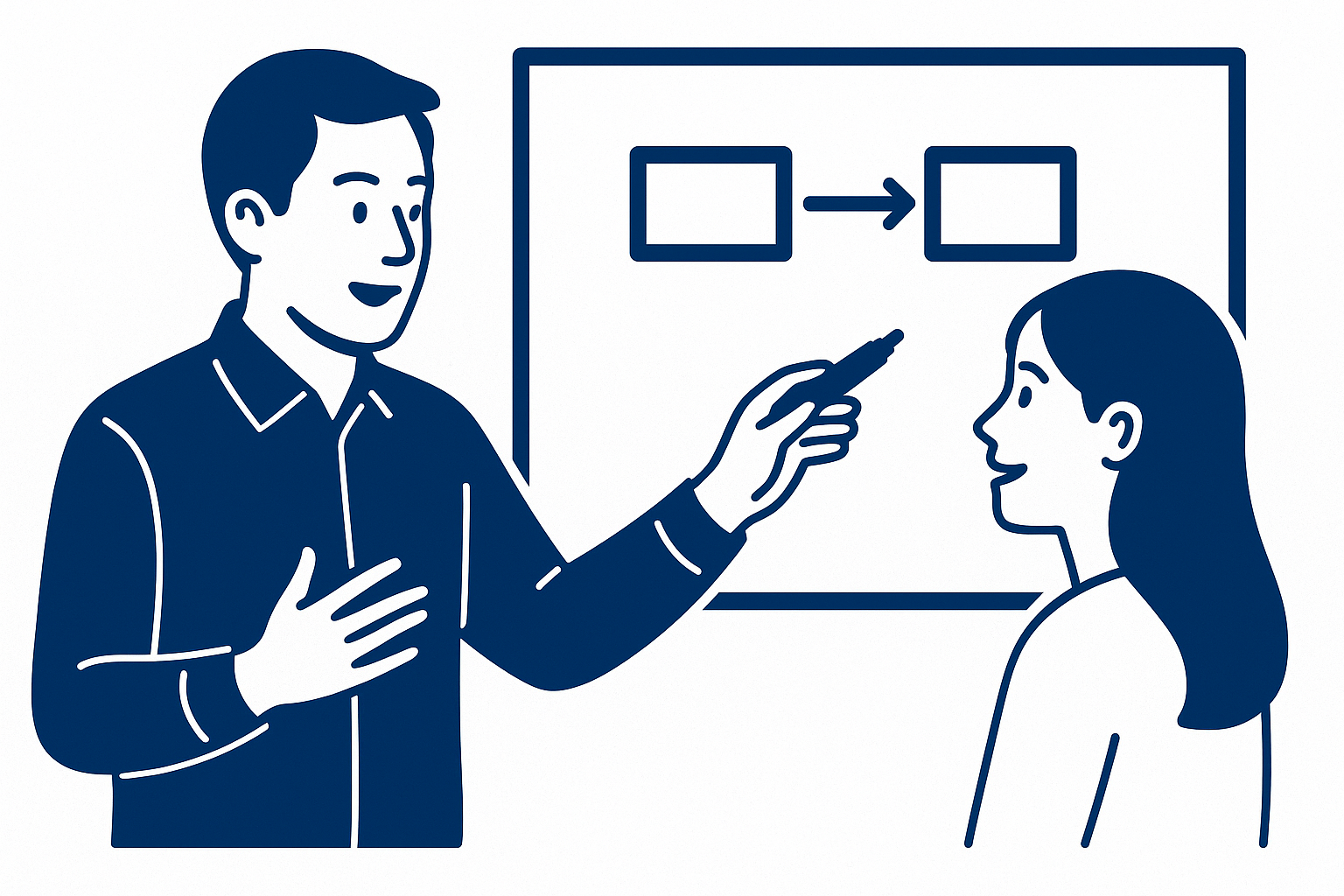
4. 注意点:ジェスチャーにも文化的背景がある
留学生とのコミュニケーションや、多様な文化的背景をもつ学生と接する場合、ジェスチャーが誤解を生む可能性に注意が必要です。
例えば、日本で一般的な「手のひらを下にして招く」動作は、他国では「拒否」や「追い払う」意味になることもあります。


「足を組む」ことも、米国では親愛を示すとされますが、日本では特に目上の人に対しては失礼とされる可能性があり、文化的な差異がありそうです。
ジェスチャーの意味は文化依存性が高いため、「安心させるつもりが逆効果だった」という事態を防ぐには、
相手の反応を丁寧に観察しながら、状況に応じて柔軟に使うことが大切です(Matsumoto & Hwang, 2013)
Matsumoto, D., & Hwang, H. S. (2013). Nonverbal Communication: Science and Applications. Sage Publications.5.
5. まとめ:ジェスチャーは“もう一つの言語”
(1) 学生支援におけるコミュニケーションでは、言語と非言語のバランスが非常に重要です。
(2) その中でも「ジェスチャー」は、言葉では伝えきれない“気持ち”や“態度”を届けるもう一つの言語として、大きな役割を担っています。
(3) 特に大学生は、緊張や不安の中で言葉をうまく表現できない場面も多くあります。そんな時こそ、教職員のうなずきや手の動きといった非言語的なサインが、学生の安心感や信頼感を支える力になります。
(4) もちろん、ジェスチャーは文化や個人の感じ方によっても受け止め方が異なります。
だからこそ、自分の何気ない身振りや態度が、学生にどんなメッセージとして伝わっているかを意識することが大切です。
(5)まずは日常のやりとりの中で、ご自身のジェスチャーを「観察し、意図して活用する」という姿勢を持つことが、学生にとって「話しやすい」「安心できる」教職員像づくりにつながるはずです。


